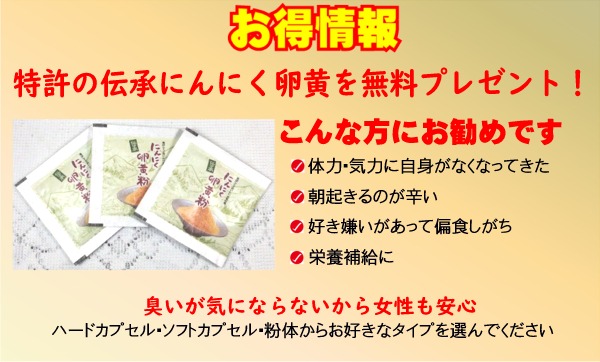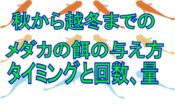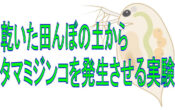メダカの卵の採取方法・簡単、手間いらずな2つの取り方

屋外飼育のメダカが採卵床にブリブリ卵を産みつけています。
このページはメダカの卵をどのよう取ってふ化させ、稚魚にするのか、簡単で手間いらずな方法を2つ紹介します。
・メダカの卵を取ってふ化させるベスト2の方法
親メダカは自分の生んだ卵やふ化した稚魚を食べてしまいます。
特に稚魚になって動き出すと標的になりやすくなります。
メダカの稚魚は大きなビオトープなど、隠れる場所がふんだんに有れば生き延びる個体もいますが、水槽で飼育している場合、基本は卵と親は隔離して管理します。
では、昨年までメダ活じいさんがやっていた方法から・・・。
もくじ
産卵床をふ化容器にドボン
昨年までメダ活じいさんがやっていた方法は、卵がついた産卵床や水草を稚魚を育成するふ化容器にドボンと投入するだけの方法です。
そして、卵のついてない産卵床を親の飼育容器に改めて投入します。
メダカの卵は積算温度が250℃と言われていますから、20度の水温の場合、産卵床に付いた卵は約2週間でふ化すると考えて産卵床を使い回ししました。
ふ化容器に投入する方法のメリットとデメリット
産卵床をふ化容器に投入する方法のメリットとデメリットを書いてみます。
メリット
・時間も手間もいりません
・天然の水草から人口の産卵床まで、全てのタイプに応用できます
・大きめのふ化容器があれば、ドンドン産卵床を投入するだけです
・ふ化容器がグリーンウォーター化していれば、ふ化した稚魚の餌になります
デメリット
・卵がふ化するまで産卵床が再利用できないので産卵床の数が有る程度必要です
・卵に付着糸が付いたままなので、汚れがつきやすくカビが発生するリスクが大です
・無精卵や死んだ卵も選別しないので、カビが発生するリスクが大です
でも、この方法はとにかく簡単で手間いらずです。
私はヒメダカの時代から昨年まで何十年もの間、この方法でメダカを絶やさずに飼い続けていました。
YouTubeですと、媛めだかさんの「メダカの卵の管理方法について稚魚が孵るまでの育て方を簡単にご紹介」と同じです。↓参考にしてください。
親抜き
次に手間のいらないのが親抜きと言われる方法だと思います。
飼育水の容器から、親だけを別の容器に移します。
親抜きのメリットとデメリットはおよそ次のようなものです。
メリット
・産卵床に産み付けられなかった水底の卵も100%ゴッソリと回収が可能
・ふ化容器がグリーンウォーター化していれば、ふ化した稚魚の餌の心配が有りません
デメリット
・親メダカを移す容器がたくさん必要です。(3日~7日で移動)
・親メダカと移動する容器の「水合わせ」に手間と時間がかかります
・卵に付着糸が付いたままなので、汚れもつきやすくカビが発生するリスクが有ります
・無精卵や死んだ卵もそのままなので、カビが広がる恐れもあります
正直、メダ活じいさんは「親抜き」という方法をやったことは有りません。
でも知人に聞くと、とにかくたくさんの稚魚が孵化すると言います。
ブリーダーにはお勧めの方法だと思います。
YouTube動画から、としやん日記の
「【親抜き後の衝撃映像】メダカの種親を抜い水槽を見たら針子が爆発的に孵化していた!スピード繁殖の方程式!」をご覧ください。
メダカ愛好家の一般的なメダカの卵の採取方法
今年、メダ活じいさんは少し面倒ですがメダカ愛好家の一般的なメダカの卵の採取方法を行っています。
つまり、産卵床に産み付けられた卵を1粒ずつ指でつまんで転がし、付着糸を取って孵化容器に入れています。
生きた受精卵は人差し指と親指で挟んでも潰れません。
白く濁った無精卵は簡単につぶれるので選別もできて一石二鳥です。
指でつまんでいる理由は、今年から煌(きらめき)と、松井ヒレ長幹之というメダカを飼い始めたからです。
今までぞんざいに扱っていた楊貴妃とスーパーブラックも同じようにしています。
えこひいきや差別はメダカに対して失礼ですから・・。
でも、そのうちに産卵床や水草をふ化容器にドボン・・・という事になるかもしれません。
まとめ
屋外飼育のメダカが採卵床にブリブリ卵を産みつけています。
このページはメダカの卵をどのよう取ってふ化させ、稚魚にするのか、簡単で手間いらずな方法を2つ紹介しました。
以前からメダ活じいさんが実行していた「産卵床をふ化容器にドボン」と「親抜き」という方法です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()
・100均のセリアはメダカグッズが超充実!水槽、容器、産卵床等お勧め用品
・セリアに有ったら買うべきメダカグッズは産卵床、うきわ、チュール生地等