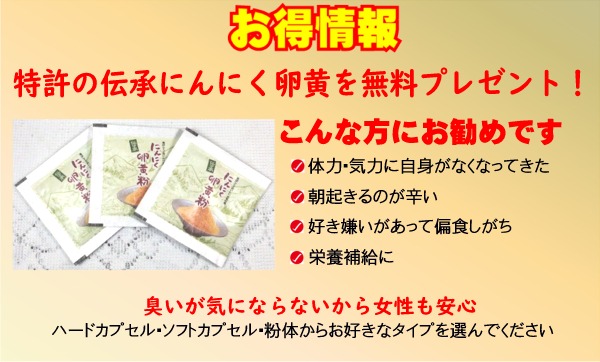屋外飼育のメダカを冬眠(越冬)明けに死なせない餌の与え方

2月も中旬になると穏やかで暖かな日が続くことがあります。
屋外飼育のメダカの水槽を覘くとメダカが水面に浮いている日もあります。
愛らしくて、つい餌を与えたくなるのですがチョット待ってください。
むやみに冬眠(越冬)明けのメダカに餌を与えると、星にしてしまうリスクが高いので気をつけましょう。
・冬眠明けのメダカを死なせない餌の与え方
もくじ
メダカは冬眠する?
まず、お断りですがメダ活じいさんはメダカは冬眠をしていないと思います。
その根拠は真冬でもメダカを刺激すると、かなり敏感に反応して泳ぎ出します。
眠っていません。
捕食や身体を動かすのを止めて、代謝も低下させて体力を維持、命を繋いでいるのです。
でも、メダ活をしている人の大半がメダカの冬越しを「冬眠」と表現しています。
ですから本記事では冬眠(越冬)と併記していますが、メダカの冬越し=冬眠ということでご理解願います。
そして、冬眠(越冬)後のメダカは取り扱いを間違えると死んでしまうリスクが高いのが現実です。
メダカが冬眠明けに死んでしまう3つの原因
メダカが冬眠明けに死んでしまう主な原因は次のようなものが考えられます。
1,餌の与え過ぎ
2,大量の水替え
3,水槽の掃除や移動などの環境変化
今日は冬眠明けのメダカへの餌の与え方ついて書いてみます。
冬眠明けのメダカを死なせない餌の与え方
メダカの冬眠明けは地域によって違いますが3~4月だと思います。
日照時間が長くなると、水が少しずつぬるんできます。
水温が10℃を超える日があってもむやみに餌を与えない方が無難です。
無事に冬眠から覚めたメダカの体調は、まだ万全ではありません。
この時期に晩春や夏、秋の感覚でメダカに餌を与え過ぎると死んでしまうリスクが高いのです。
冬眠明けのメダカに餌を与えるタイミング
冬眠明けのメダカに餌を与えるタイミングは3日以上連続して飼育槽の水温が10℃を超えるようになってからでよいと思います。
一時的に水温が上がっただけでは越冬が終わったとは言えません。
この時期のメダカは活性が落ちています。(ここでいう活性は、動きではなく内臓も含む体全体の代謝を指します)
一時的に水温が上昇すると餌を求めて捕食しますが、その後に水温が下がると消化不良を起こします。
餌を与える事が無事に冬を越したメダカに大きなダメージを与える可能性があるのです。
水温を目安にするなら安定して10℃を超え、水温が上り調子になってからです。
大きな池やビオトープなら水面が綺麗になってから餌を与え始めます。
メダカが冬の間に水面に落ちたゴミを食べたりつついたりするため、ゴミが無くなったり小さなゴミが水中に沈んで水面が綺麗になるのです。
どちらの餌やりも、一日に一回、少量の餌を与えます。
食べた後に水温が上昇傾向になる昼ごろ餌やりがベストです。
暖かくなるまでは、餌を食べた後に水温が下がる夕方の餌やりは控えましょう。
冬眠明けのメダカの餌は消化の良い餌を少なめに
冬眠明けのメダカの餌は消化の良いものを選びます。
新たに購入するなら、タンパク質や脂質の少ないパウダー状の餌で「消化が良い」と書いてある品がおすすめです。
粒タイプの餌をお持ちなら、すり鉢などですりつぶして物理的に消化しやすくしてあげましょう。
水温が上昇傾向にある時期と時間なら餌の量は少なめで2~3分以内に食べきる量が良いと思います。
水温が下がった日は餌を与えないようにします。
活性が低く、あまり餌を食べない時期に食べ残しの餌があると水質の悪化につながります。
水質の悪化もメダカが死ぬ原因となりますので注意が必要です。
後は様子を見ながら順次餌の量を増やしてメダカに体力をつけていきます。
まとめ
冬眠(越冬)明けのメダカにむやみに餌を与えると、星にしてしまうリスクが高いので気をつけましょう。
飼育槽の水温が3日以上連続して10℃を超え、その後も水温が上昇傾向になってから消化の良い餌を少しずつ与えましょう。
後は様子を見ながら順次餌の量を増やしてメダカに体力をつけていきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()