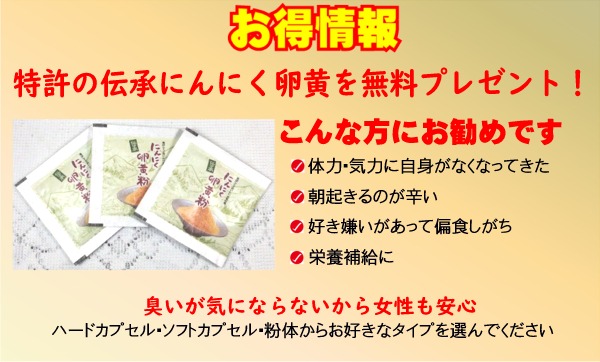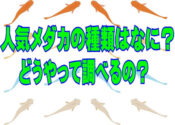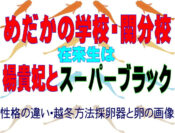ダルマメダカの転覆病は早期発見なら簡単な治療で治せる!

屋外飼育のメダカの水温が下がって、ダルマメダカの転覆病が続発しています。
たまらず屋外越冬用に準備した底の深い発泡スチロール容器を室内に運びこみました。
水温を上げてやると転覆していたダルマメダカが正常に泳ぎ出します。
前回のダルマメダカが転覆病に!急いでやるべき対策と治療法では、メダ活じいさんも初めての経験で泡を食いました。
しかし、ここへきてダルマメダカの転覆病は早期発見なら簡単な治療で治せることが判りました。
ダルマメダカの転覆病でお困りのあなたと情報を共有したいと思います。
・ダルマメダカが転覆病に罹る理由
・飼育水の温度を上げれば転覆病は治る
もくじ
ダルマメダカが転覆病に罹る最大原因は水温の低下
そもそも、ダルマメダカが転覆病に罹る原因はなんでしょうか?
飼育水の水温が下がってくると転覆病が発症する子が出てきました。
その後、秋深くなって気温が下がり、水温が15℃を割り込むと別の子が転覆しました。
さらに、朝の水温が6℃~7℃になると、またまた転覆する子が2匹も出てきました。
しかしながら、水温が6℃を割り込んでも転覆病に罹らないダルマメダカもたくさんいます。
ダルマメダカが転覆病にかかる水温には個体差があるのです。
コンニチワン🐶
本日もよろしくお願いします🙇♂️⤵️岐阜県の気温は14℃まで上がる予報。
屋外越冬を予定していたダルマメダカが2匹も転覆しそうになり、急きょ2つの発泡を室内に移動しました。
水温9℃なら正常に戻りますが7℃を切ると…
何とも無い子もいるのですが。 pic.twitter.com/Tyhmnq1ewv— メダ活じいさん (@medaka_seki) December 5, 2022
ダルマメダカの転覆病は水温を上げれば正常に泳ぎだす
ダルマメダカの転覆病は、早期発見なら飼育水の水温を上げてやれば、ほとんどの子が正常に泳ぎだします。
事実、水温が6℃~7℃で転覆した子をボウルで塩水浴させて室内に避難させて、水温が10℃以上になったら復活したのです。
その後、塩水浴を止めてボウルから出してやりましたが、水温10℃前後なら元気に泳いでいます。
水温低下がダルマメダカの転覆病を招く理由
ダルマメダカが転覆病に罹る理由は、普通のメダカよりも体長が短く、まるまるとした愛くるしい体型にあります。
まずは、まぁ~るい、コロコロした体型のダルマメダカが生まれる理由から・・・。
ダルマメダカの体長が短い理由
体長が短い理由は、fu遺伝子という全てのメダカが持っている遺伝子によるものです。
fu遺伝子は脊髄を短くする遺伝子ですが、環境や状況によって普通体型のメダカが生まれたり、ダルマ体型になったり、中には中間のセミダルマ体型になったりします。
夏場に水温が30℃以上の環境で卵が孵化すると、ダルマメダカやセミダルマの出現率が高くなります。
ダルマメダカは脊髄の数が少ないという説と、脊髄の数は同じですが癒着して体長が短くなっているという説があります。
その短い体の中に普通体型のメダカと同じ内臓がギュッと押し込まれているのです。
そのため、臓器が圧迫されてお腹がまぁ~るく出っ張っているのです。
水温低下がダルマメダカの転覆病を招く理由
ダルマメダカが転覆病に罹る理由は、出っ張った腹部に収まっている消化管にあると思います。
もともとダルマメダカは、餌をたくさん食べると身体のバランスがとりにくくなる体型です。
体型と転覆病の関連で参考になるのが、琉金という金魚です。
琉金もダルマメダカと同じようなまぁ~るい体型をしていて、物理的に転覆病になりやすい魚なのです。
加えて、メダカは水温によって 消化管の活動が変化します。(金魚も同じですが・・・)
具体的には、水温が23℃以上だと活性が高く餌をたくさん食べます。
反対に水温が15℃を切ると活性が低くなり、餌をあまり食べなくなります。
活性の低下は消化能力の低下も招き、消化不良を起こしやすくなるのです。
ヒトに例えると、お腹にガスが溜まったり、食べたものを排出できなくなった状態で転覆するのだと考えられます。
転覆病を起こしやすいダルマメダカには、消化の良いエサを与える事や、食べ過ぎないようにセーブする必要がありそうです。
ストレスもダルマメダカの転覆病の原因に!
水温低下と消化不良の他に、ストレスもダルマメダカの転覆病の原因になります。
体型から泳ぎの苦手なダルマメダカは強い水流もストレスになります。
また、過密飼育や水質悪化もストレスです。
転覆病に罹ったダルマメダカには、体力の回復とストレスの緩和に塩浴が有効です。
塩浴の詳細はメダカを塩浴させる意義をご覧ください。
本当にダルマメダカの転覆病は治ったのか?
さて、ここで問題です。
本当にダルマメダカの転覆病は治ったのでしょうか?
ダルマメダカの転覆病を病気の症状と捉えれば治ったことになる
ダルマメダカの転覆病を病気の症状と捉えれば治ったことになります。
ヒトに例えると花粉症の人が毎年同じ花粉で発症して、その花粉の時期が過ぎると「治った」と言うのと同じです。
しかし、この状態は病気が完全に治った、すなわち治癒(ちゆ)したのではありません。
病気による症状が無くなった状態なので寛解(かんかい)なのです。
しかし、ヒトの花粉症も転覆病に罹ったダルマメダカも、症状に悩まされることなく快適な日常が過ごせます。
個体差はあるものの、水温を上げてやれば転覆しないのですから・・・。
ダルマメダカを飼育する推奨水温は28~30℃だと言われています。
ダルマメダカをグッピーや熱帯魚と同じ感覚で飼育する人なら、治ったも同じだと考えて良いと思います。
ダルマメダカの転覆病を体質と考えると治っていないと言える
ところが、ダルマメダカの転覆病を体質だと考えると治っていないと言えます。
水温を下げると、以前に転覆した水温と同じくらいの水温で再度、発症するからです。
この体質を変えるには、体型を変えるしか方法は無いと思います。
つまり、外科手術が主な手法になると思います。
たぶん、ダルマメダカに手術を施すのは不可能でしょうね。
まとめ
ダルマメダカの転覆病は早期発見なら簡単に治せることが判りました。
具体的には転覆病に罹った個体には塩浴をさせ、水温を上げてやれば正常に泳ぎ出します。
しばらく様子を見てから徐々に水温を他のダルマメダカと同じに戻します。
再び転覆するようであれば、熱帯魚を飼うのと同じ感覚で飼育水温を28~30℃で維持してあげてください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()