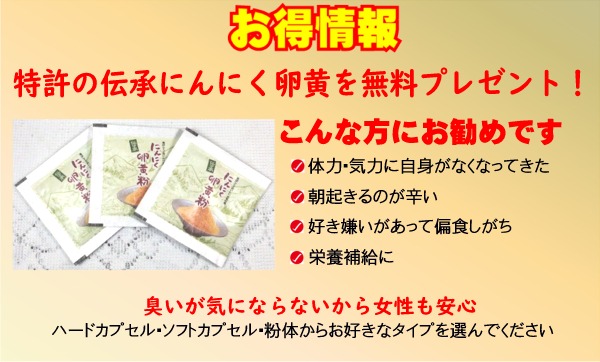冬眠(越冬)後のメダカを死なせない為の注意点の3つ目は環境変化

昨日、屋外で越冬中のメダカを全て覚醒させました。
飼育水槽は1つの石臼と6つの発泡スチロール箱です。
昨年の晩秋に孫が岐阜畜産センターでいただいてきた幼魚5匹のうちの1匹が星になっているのを発見しましたが、後はみんな元気です。
メダカを全て覚醒させた後に、赤く光る遺伝子組換えメダカのニュースをテレビで見ました。
(赤く光る遺伝子組換えの)ミナミメダカはヒレや骨の再生などの研究目的で「イソギンチャクモドキ」の遺伝子が組み込まれていて、紫外線に当たると赤く光るということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e446d8beb36fe15e9992e45cf8032182fdf759f4より
メダ活じいさんは、楽しく、まじめにメダカの飼育をしています。
遺伝子組換えメダカはもちろん、改良メダカの放流もご法度ですよ。
今日は冬眠(越冬)後のメダカを死なせない為の3つ目の注意点を書いてみます。
今期の屋外メダカの冬眠(越冬)は大成功
今期の屋外メダカの越冬は大成功でした。
水槽を掃除したわけではありませんが、(後述しますが、未だ掃除しない方が良いです)目視の限りでは「無事に越冬できるかな?」と心配した孫の幼魚を1匹落としただけですから・・・。
では、越冬後の動画をご覧ください。
コンニチワン🐶
岐阜県関市の気温は20℃。
今日、越冬中のメダカを覚醒させました。
楊貴妃、煌、松井ヒレ長幹之と煌です。 pic.twitter.com/vjl1ZDIgQu— メダ活じいさん (@medaka_seki) March 8, 2023
左動画の楊貴妃の水槽は飼育水が透明になっています。
その為か、若干スマートになった子がいます。
右上の煌の飼育水は少し青水がかって(グリーンウォーター化して)います。
痩せている子はいません。
右下の石臼の松井ヒレ長幹之と煌の水も青水がかっています。
個体は小さめですが、やせた子はいません。
詳細は「メダカの越冬用に準備しておきたい天然グリーンウォーターとその理由」をご覧ください。
動画や画像は有りませんが、孫がもらってきた生き残りの幼魚が大きくなっていた事です。
では、越冬後のメダカを死なせない為の注意点の3つ目について・・・
越冬後のメダカを死なせない為の注意点の3つ目は環境変化
屋外飼育のメダカを冬眠(越冬)明けに死なせない1つ目は餌の与え方、2つ目が水換え方法でした。
そして3つ目が環境変化です。
冬眠明けのメダカの体調は未だ万全ではありません。
この時期にいきなり水槽の掃除をすると、メダカだけでなく水中のバクテリアにも大きな影響をおよぼして水質が不安定になります。
また、「少しでも暖かい場所に・・・」などと気を利かせて日当たりの良い場所に水槽を移動させると、天気の良い日中と夜間の水温の変化が激しくなります。
ヒトでも寒暖差の激しいこの時期は体調不良になりがち。
メダカも同じです。
メダカの体調が万全になり、落ち着くまでは容器の移動はせずに越冬中と同じ場所に据え置き、環境を大きく変えないようにします。
メダ活じいさんの場合は、越冬中は飼育槽に波板をかぶせていましたので、夜間の気温が下がるような日には波板をかぶせるようにしています。
余談ですが、メダ活じいさんの知り合いは、昨シーズンで5年間も生存しているメダカを飼っています。(大きいですヨ)
南向きの玄関の軒下で雨が入らない陶器の中で飼われているのですが、ズ~ッと同じ場所で飼われています。
環境の変化が穏やかだと長生きするのでしょうね。
まとめ
昨日、屋外で越冬中のメダカを全て覚醒させました。
メダカは冬眠明けに死んでしまうことが多いのです。
越冬後のメダカを死なせない為の注意点の3つ目、「環境の変化」について書いてみました。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()
・屋外飼育のメダカを冬眠(越冬)明けに死なせない餌の与え方
・冬眠(越冬)後のメダカを死なせない水換え方法