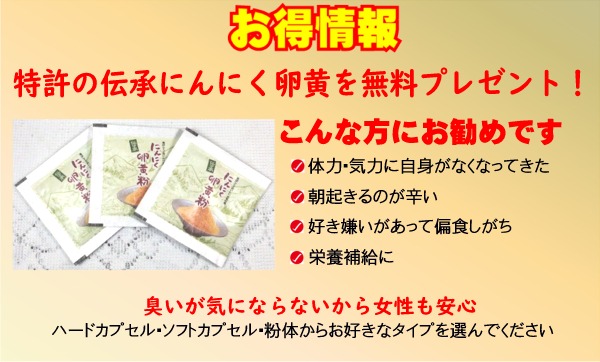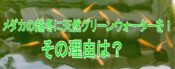メダカの採卵を9月中旬に止める理由・屋外飼育の場合
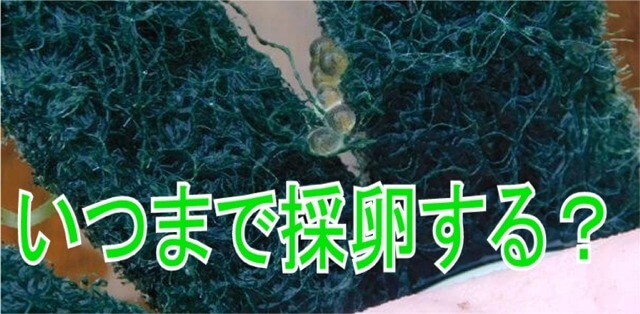
今年は残暑が厳しいです。
日差しが強く9月中旬だというのに岐阜県で35℃です。
ここ連日、屋外飼育のメダカには簾をかけなければなりません。
屋外飼育のメダカさん達は卵を産んでいるのですが、メダ活じいさんは採卵(卵を取る行為)を止めています。
メダ活じいさんは、毎年8月末頃からメダカの採卵をしません。
屋外飼育のメダカの産卵時期は?
その理由を書く前にメダカの産卵時期を記述しておきます。
この地方の屋外飼育のメダカは、だいたい4月中旬から10月中旬まで産卵します。
春に生まれたメダカは、夏には親と区別がつかないくらいまでに育ち、早生まれの子は身体は親より一回り小さいのですが、6月には産卵を始めます。
メダカが産卵していても採卵をしない理由
9月~10月もメダカが産卵しているのにメダ活じいさんが8月末から採卵をしない理由は・・・
今までの経験から8月のお盆を過ぎてから生まれた子は、大きくて丈夫な子には育ちにくいからです。
そして、屋外越冬させるのに懸念が残るのです。
メダカの稚魚は屋外で冬越しができるか?
メダカの稚魚は屋外で越冬できるでしょうか?
メダカをサイズを目安にして呼び名で表すと
●針子:7mmまで
●稚魚:8~13mm
●幼魚:14~19mm
ざっと上記のようになります。
10mm越えの稚魚でも越冬はできます。
しかし越冬中や冬を越した直後に、大きなメダカとの餌の争奪戦に負けてしまい、いつまでも一番小く、ひ弱な個体が多いのです。
ですからメダ活じいさん的には、越冬は幼魚の大きさ(14~19mm)以上が望ましいのです。
9月~10月から卵が孵化していては、冬を越すまでに十分な大きさに成長する期間が短すぎるのです。
もし水温を上げて卵の孵化を促進し、針子にはゾウリムシ、稚魚になったらミジンコを与えて特別早く大きくできる方はこの限りではありませんが・・・。
メダカの稚魚を早く大きな若魚にするには選別が重要!他・・・を参考にしてください。
メダカの飼育で9~10月に注力すべきこと
メダカの屋外飼育で9~10月に注力すべきことは、針子や稚魚、幼魚を少しでも大きくして越冬できる身体に仕上げてやる事です。
もちろん、少しでも快適に越冬できる準備を整える事も大切ですが・・・。
まとめ
屋外飼育がメインのメダ活じいさんは、毎年8月末頃からメダカの採卵をしません。
理由は、8月のお盆過ぎから生まれる子は経験則から丈夫で大きな個体に育ちにくいからです。
屋外での越冬も考慮に入れると、遅くても9月の中旬には採卵を止めた方が良いと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()