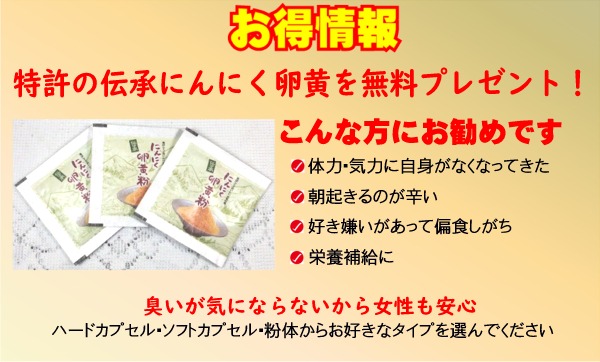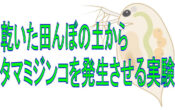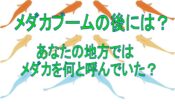めだかの学校・関分校の在来種は楊貴妃とスーパーブラック
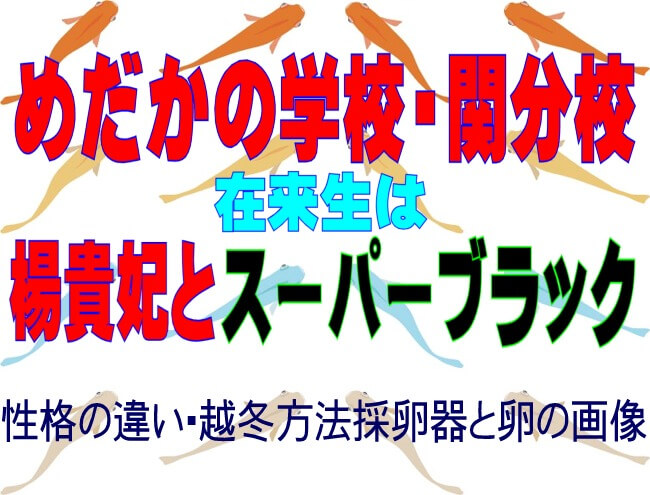
3月12日にめだかの学校・関分校へ転校生の煌(きらめき)の稚魚が11匹と松井ヒレ長幹之の稚魚が12匹やってきました!
どちらも、水合わせが無事に済み、屋外飼育で既に稚魚用の餌を食べています。
今日はめだかの学校・関分校の在来種のご紹介をします。
めだかの学校・関分校には楊貴妃とスーパーブラックが在校しています。
・楊貴妃とスーパーブラックの性格の違い
・越冬方法
・メダカの採卵器と卵の画像
コロナ禍の今年も、屋外で元気に越冬した楊貴妃とスーパーブラックは、冬眠明けの餌も順調に食べています。
今まで飼育、繁殖していたメダカは楊貴妃とスーパーブラック
昨年までめだかの学校・関分校で飼育、採卵、繁殖、累代を重ねていたメダカは楊貴妃とスーパーブラックの2種類です。
今までめだかの学校・関分校のメダ活じいさんが飼った経験のあるメダカは、小学生の3~4年生の夏休みに父親に買ってもらったヒメダカ、社会人になってから川で捕獲した野生の黒メダカ、知人からいただいた白メダカ、(種類とは言えないかもしれませんが、ダルマメダカ)と楊貴妃、スーパーブラックです。
その中で今も飼っているのが楊貴妃とスーパーブラックです。
趣味で飼育、繁殖をしているだけなので、増えたメダカは無料で知人に配っています。
プロでは「ありませんから、メダカの飼育方法はずぼらでいい加減です。
肩の力を抜いてご覧いただければ幸いです。
楊貴妃とスーパーブラックの画像と性格の違い
飼い方にもよりますが、楊貴妃とスーパーブラックの性格は全く違うと思います。

メダカの楊貴妃(左)とスーパーブラック(右)の画像
冬眠が明けて餌やりを始めてから、ほぼ2週間になりますが、左の画像の赤い楊貴妃は人の足音や気配が近ずくと、水面に浮き上がってきます。
冬眠明けとはいえ、上記画像のメダカは痩せているのが目立ちます。
オハズカシイ。
スーパーブラックは、人の足音や影が近ずくと水底深く潜って逃げるような行動をとります。
飼育メダカというより、野生の魚に近い状態です。
もう少しの間、餌を与え続けると、スーパーブラックも水面に姿を現すようになります。(例年の事です)
めだかの学校・関分校の越冬方法
2種類のメダカは、この冬も屋外の発泡スチロールのリンゴ箱で越冬させました。
水面に氷が張ってもメダカは越冬できますが、少しでも暖かく越冬できるように、ここ数年はリンゴ箱の上に透明ビニールをかぶせています。
今冬は初めて楠の枯れ葉をベッドの代りにリンゴ箱に投入しました。
本当は柿の葉が良いと投入後に知りました。(冬眠明けの餌になるようです)
現在は、楊貴妃の水槽はグリーンウォーターになっています。(このグリーンウォーターは、メダカの稚魚を育てる時に重宝します)
なぜか、ほぼ同じ条件なのにスーパーブラックの水槽は淡い藻水中を漂っていてグリーンウォーターになっていません???
メダカの採卵器と卵の画像
下図は昨年、めだかの学校・関分校で使っているメダカの採卵器に卵が産みつけられた画像です。

メダカの採卵器と卵
画像の中央付近に8粒ほど産みつけています。
採卵器はナイロンタワシとペットボトルのキャップで作った簡単なもの。
ホテイアオイなどの水草で採卵する方法も有りますが、ナイロンタワシの採卵器の方が卵が良く見えて管理が簡単です。
まとめ
コロナ禍の今年も、めだかの学校・関分校のメダカ達は元気に越冬しました。
こんな時期だからこそ、メダカを飼って心を癒すとともに、生命の神秘や尊さを身近に感じていただけるきっかけにでもなればと、現在、めだかの学校・関分校で飼育しているメダカの種類とその性格の違い、越冬方法、メダカの採卵器と卵の画像について書いてみました。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
お帰りの際には↓のバナーを「ポチッ」していただけますと幸いです メダ活じいさん
![]()